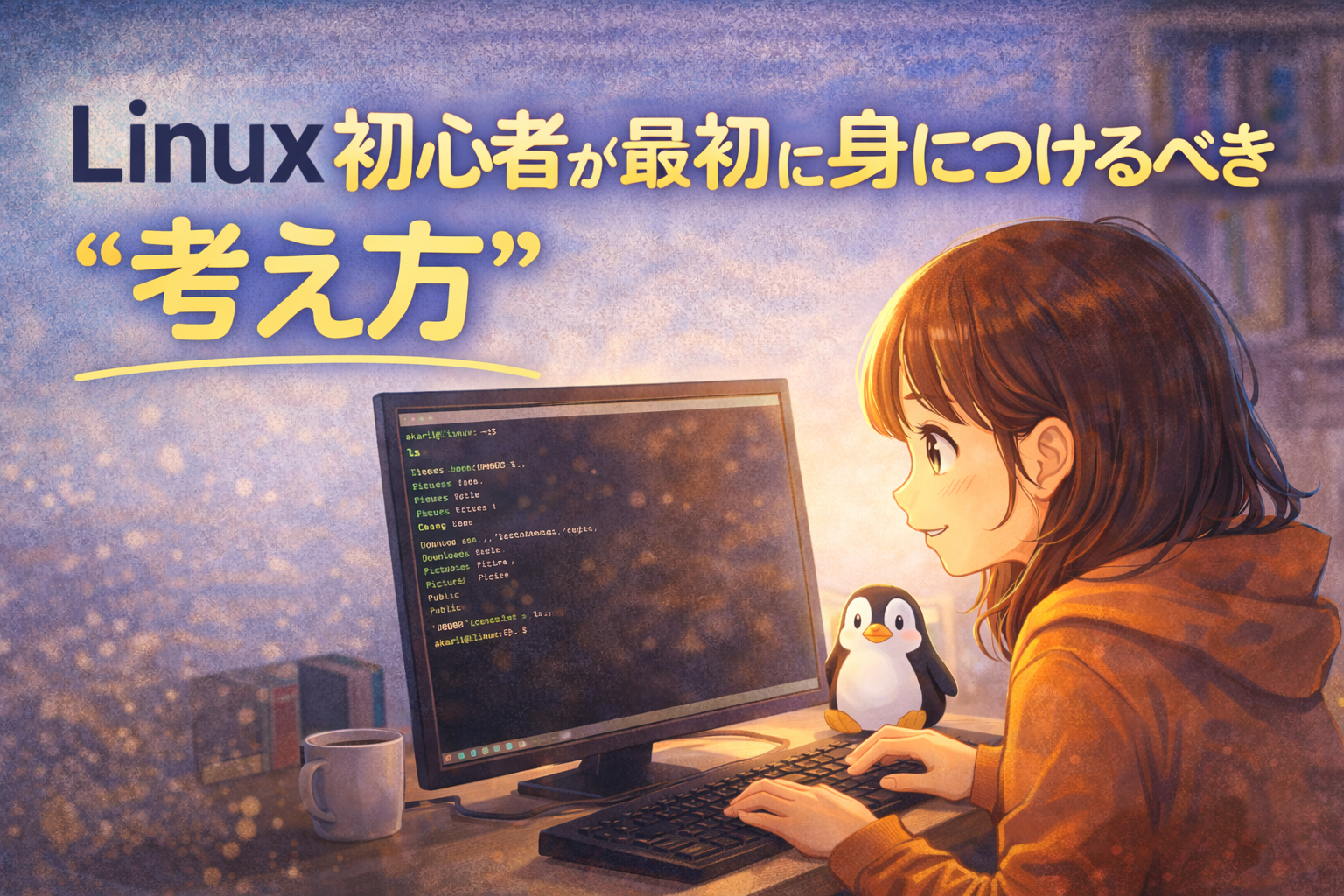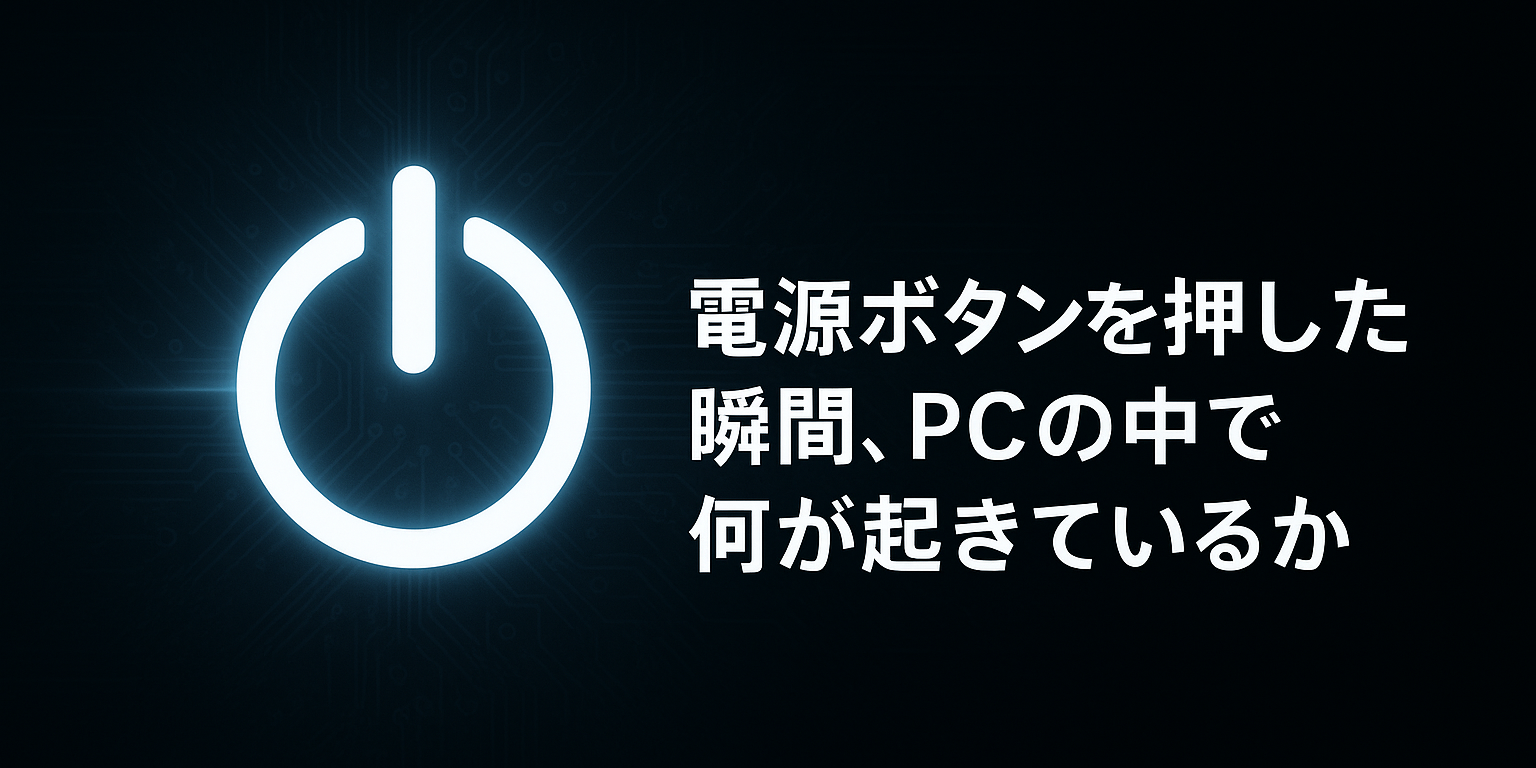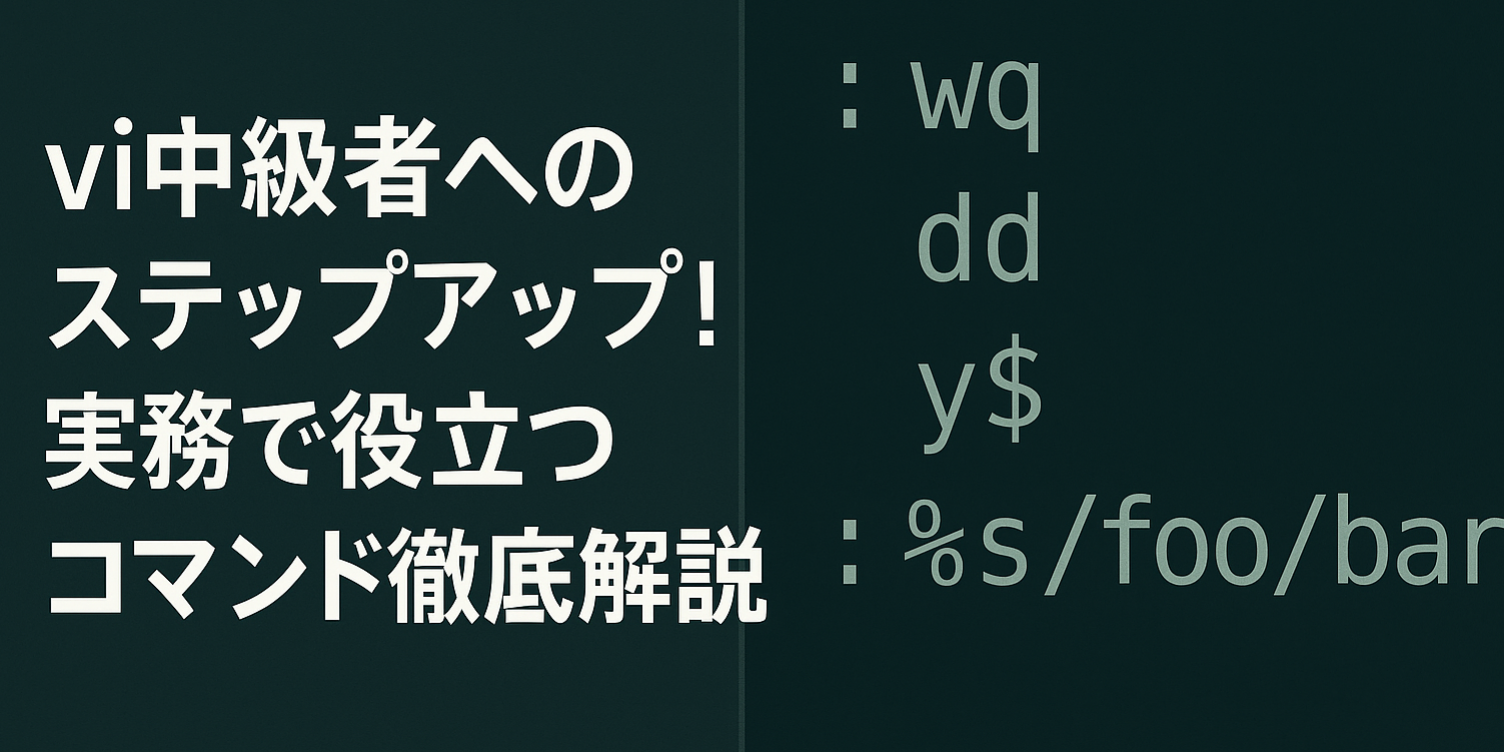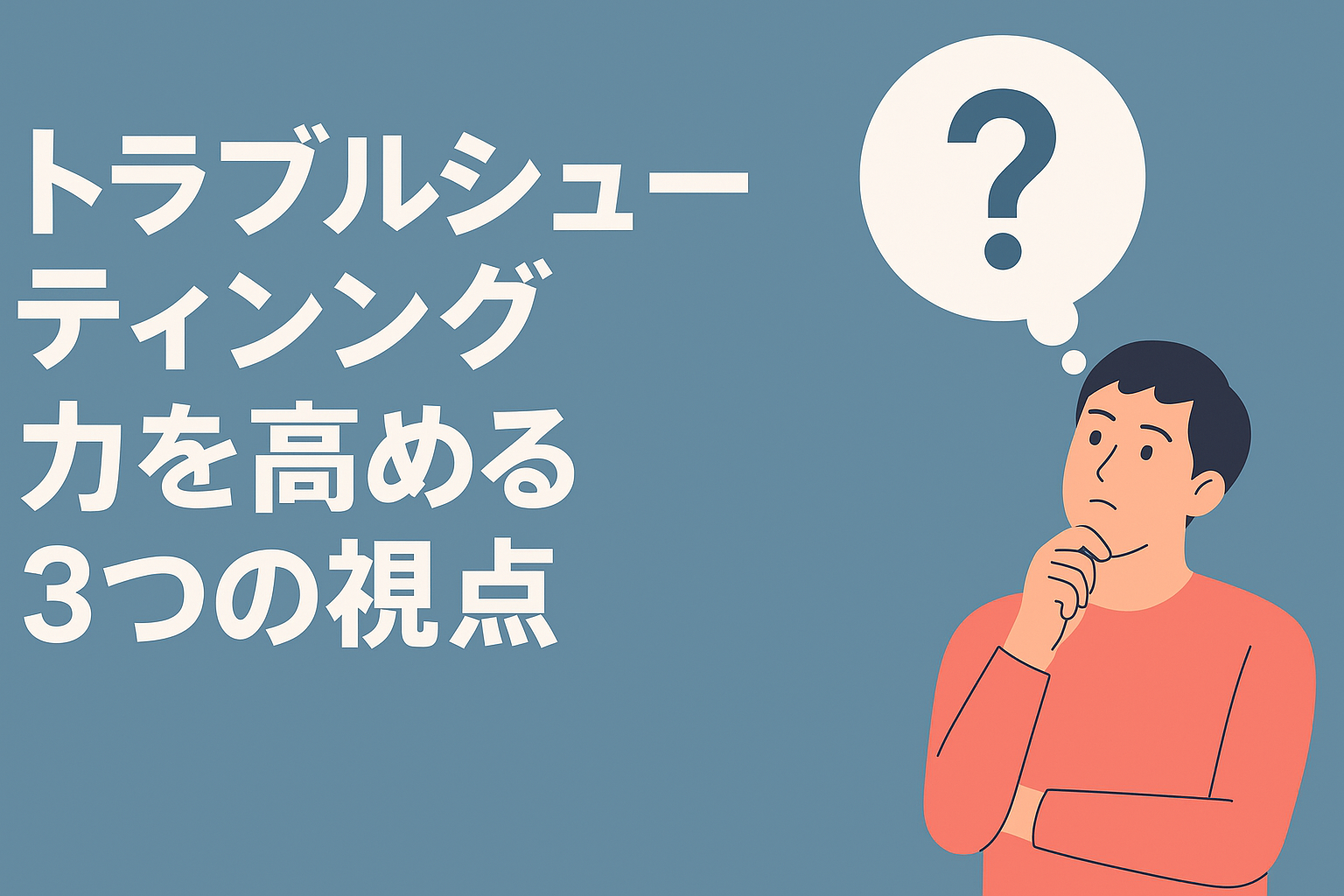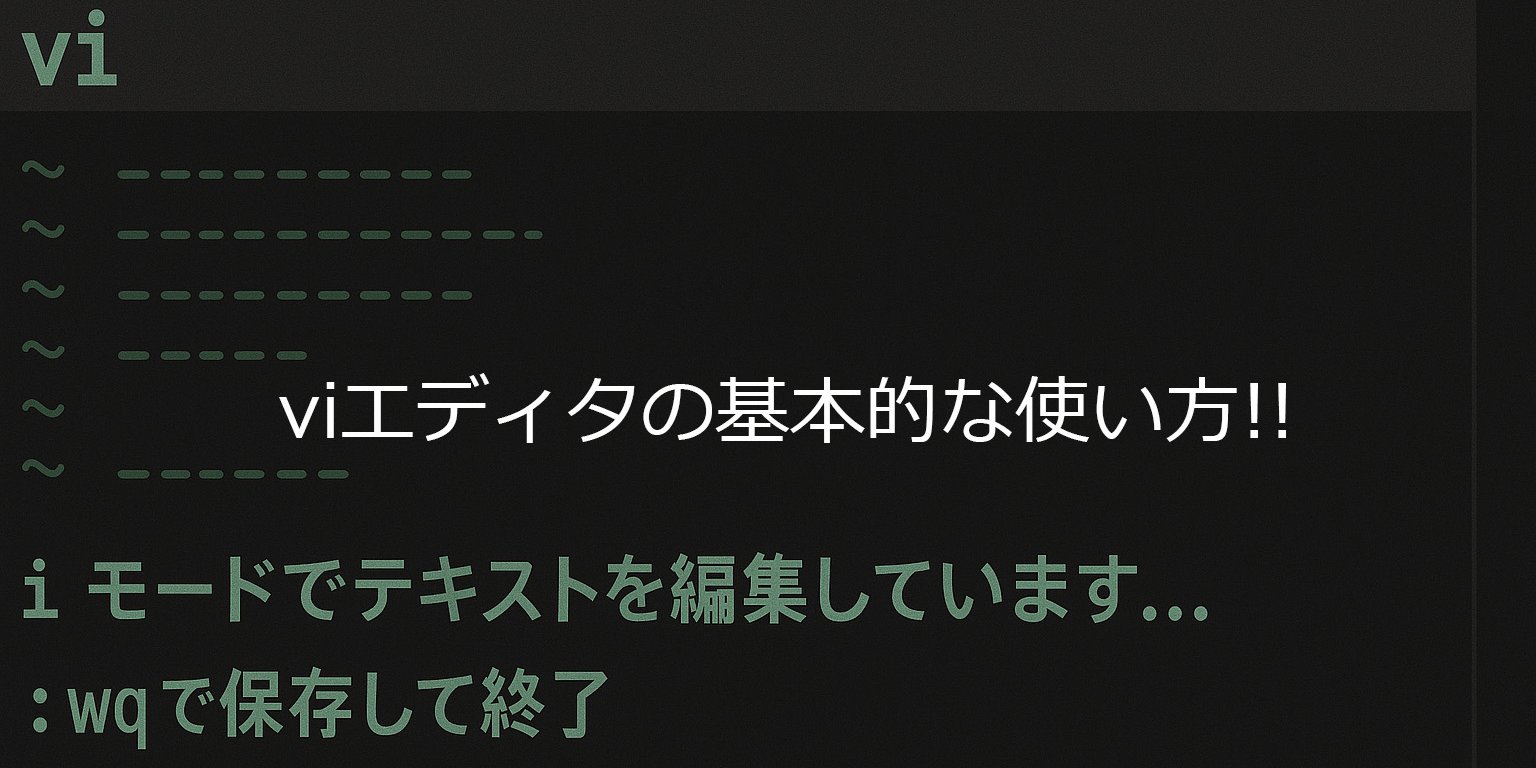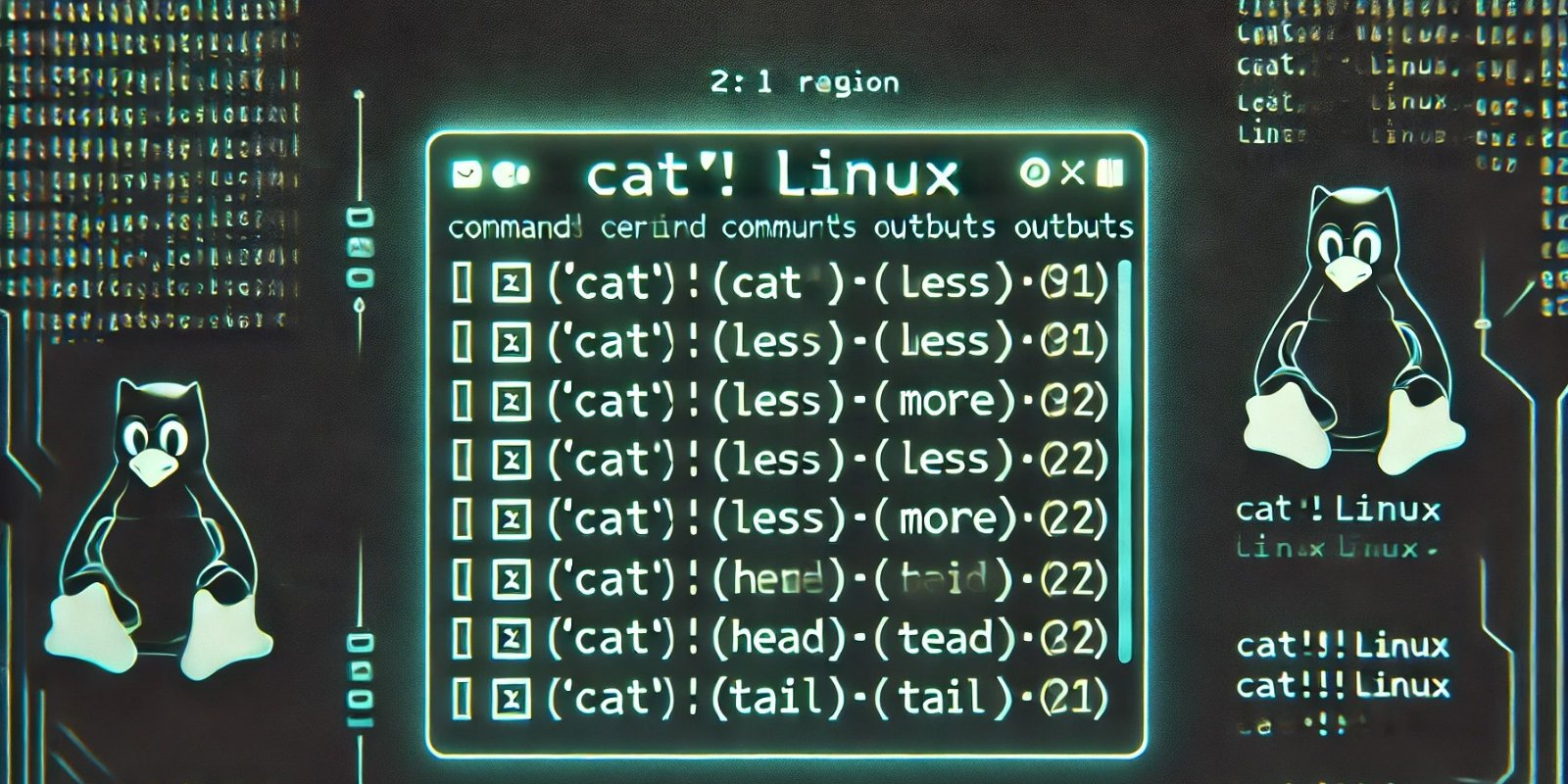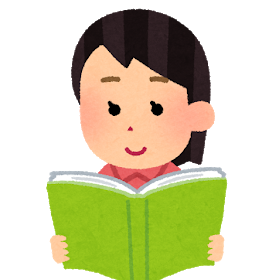株式会社グローバルゲート公式ブログ
Linux初心者が最初にハマる7つの壁とその乗り越え方
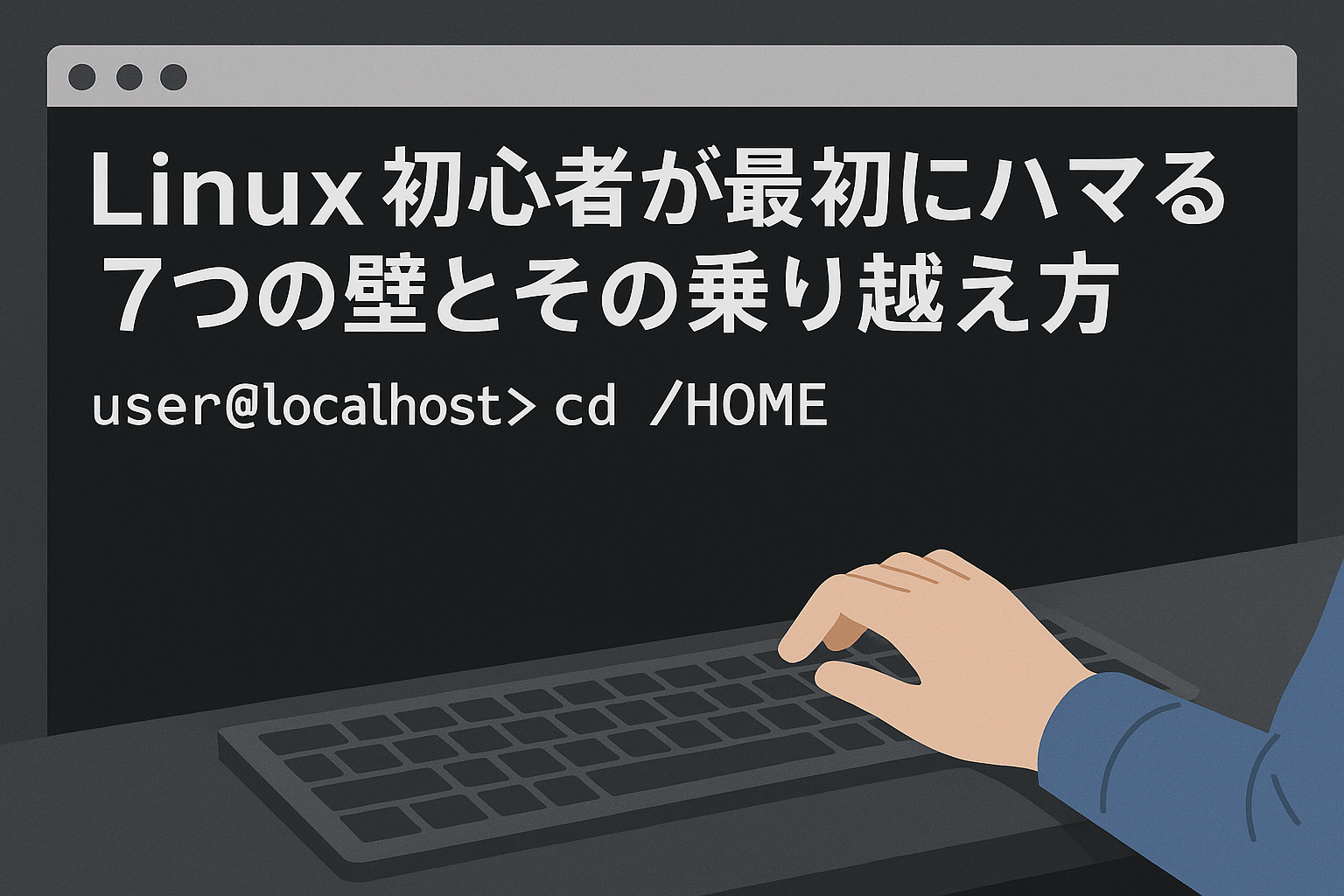
こんにちは!株式会社グローバルゲートでサーバ管理をしてるタカです。
Linuxを使いはじめたばかりの頃、「コマンドを入力しても動かない」「なんでエラーになるの?」と、パソコンの前で固まってしまった経験はありませんか?WindowsやmacOSとはひと味違う操作感に戸惑いながらも、調べて試して、またつまずいて…
そんな“壁”の連続が、Linuxの第一歩にはつきものです。
でも安心してください。実は、初心者がつまづくポイントには“あるある”なパターンがあるんです。この記事では、これからLinuxを使いこなしていきたいと思っている方のために、最初のうちに多くの人がハマってしまう7つの“壁”と、それをどう乗り越えるかを、やさしく解説していきます。
かつて同じように悩んでいた筆者自身の体験を交えながら、一歩ずつ「わかる」「できる」に変えていきましょう!
1. 大文字小文字の違いにハマる!【cdで移動できない】

Linuxを使い始めたばかりの初心者が、まず高確率でつまずくのが「大文字・小文字の区別」です。たとえば、cd Desktopと入力したのに「No such file or directory」とエラーが出る。「いやいや、絶対あるはずなんだけど?」と首をかしげながら、何度もコマンドを打ち直した経験はないでしょうか。
実は、Linuxはファイル名やディレクトリ名の大文字・小文字を厳密に区別します。つまり、Desktopとdesktopはまったくの別物という扱いになります。Windowsに慣れていると気づきにくいポイントですが、ここを理解していないと、たった1文字の違いで“存在しない”と言われてしまうのです。
よくある初心者ミスの例

このとき、Linuxは「Desktopというディレクトリは存在しない」とエラーを返します。
しかし、実際には小文字のdesktopが存在していた…というオチは“Linux初心者あるある”です。
解決策:lsで確認+Tab補完の活用
この問題を回避するには、まずlsコマンドでその場にあるディレクトリを確認するのが基本です。

これで表示された名前を正確に入力すれば、たいていの問題は防げます。さらに便利なのがTab補完機能。たとえば、

と入力すれば、該当するディレクトリ名が補完されます。間違った大文字を使っていた場合は補完されないため、ミスに気づきやすくなるのです。
実務でも要注意!
この大文字小文字問題、初心者に限らず実務でも事故につながることがあります。たとえば、スクリプトの中でファイルパスをconfig/Settings.jsonと書いていたつもりが、実際のファイル名はconfig/settings.jsonだった場合、開発環境では動くのに、本番サーバでは動かない…なんてことも。
そのため、プロジェクト内で命名ルール(小文字統一、スネークケース推奨など)を決めておくことが、意外と重要だったりします。
Linuxの世界では、「Desktopとdesktopは別物」という基本がすべての土台になります。
最初は違和感があるかもしれませんが、慣れてしまえば当たり前。むしろ「細かい違いを正しく扱える安心感」に変わっていくはずです。
小さな壁かもしれないけれど、ここをしっかり理解することで、Linuxとの付き合い方がぐっと楽になります。
2.実行できない!?【Permission deniedとの戦い】

Linuxを使っていて、シェルスクリプトやプログラムを実行しようとしたときに突然現れる「Permission denied」の文字。特に初心者にとっては、このエラーが出た瞬間、「え?なんで?壊れたの?」と焦ってしまうかもしれません。

見た目ではファイルはちゃんとそこにあるし、名前も間違っていない。にもかかわらず、実行できない。これはLinuxにおけるファイルのパーミッション(アクセス権限)に関する“壁”です。
実行するには「実行権限」が必要
Linuxでは、ファイルがあるだけでは「実行」できません。
たとえば、".sh"という拡張子がついていても、それが自動的に実行可能になるわけではないのです。
実行するには、そのファイルに「実行していいよ」という権限が付与されている必要があります。
それを確認するには、ls -lコマンドが便利です。

ここで、ファイルのパーミッションが「rw-r--r--」となっているのが分かります。
これは「読み(r)」と「書き(w)」はOKだけど、「実行(x)」は付いていない、という状態。
解決策:「chmod +x」で実行権限を追加
この問題を解決するには、実行権限を追加すればOKです。
以下のコマンドを使いましょう。

これで、実行権限(x)がファイルに付きます。

今度は、"./run.sh"で実行できるようになっているはずです!
sudoでも解決しない?
初心者の中には「sudoを付ければ何でも動く」と思ってしまう人もいますが、これは間違い。
実行権限がないファイルに対してsudo ./run.shをしても、やはり「Permission denied」は出てしまいます。
まずはファイルの属性を見て、適切なパーミッションを与えるという基本を忘れずに。
Linuxでは「実行できるファイル」と「見るだけのファイル」は明確に分かれています。
それぞれの用途に応じた権限設定が必要だからこそ、セキュリティ的にも安心な仕組みになっているんですね。
最初は戸惑うかもしれませんが、"chmod"と"ls -l"を覚えるだけで、この“壁”は簡単に乗り越えられます。
ぜひ、ターミナルの前で一度試してみてください!
3. viから出られない!【初めてのエディタ地獄】

Linux初心者が必ずといっていいほど経験するのが、vi(またはvim)からの脱出不能事件です。
設定ファイルをちょっと編集しようと開いたはずが、保存も終了もできず、最終的にはターミナルを強制終了してしまった…そんな経験はありませんか?
なぜ「出られない」のか?
viはモード型エディタで、文字を入力するモードとコマンドを実行するモードが明確に分かれています。
起動直後は「コマンドモード」という状態で、直接文字を入力しても何も起こらないように見えます。
さらに、終了するには特定のキー操作が必要なため、知らないといつまでも画面に取り残されてしまいます。
基本の終了方法
viから安全に抜け出すためには、まず Escキー を押してコマンドモードに戻る必要があります。
そのうえで、以下のコマンドを入力します。
・:wq → 保存して終了(write & quit)
・:q! → 保存せずに終了(quit without saving)
※ : を打つと画面下にコマンド入力欄が出てくるので、そこに"wq"や"q!"を入力し、Enterを押せばOKです。
編集中に保存だけしたい場合
作業を中断して後から続きを書きたいときは、

と入力することで変更を保存してviは終了せず、そのまま編集を続けられます。
よくある初心者ミス
1.挿入モードのまま終了コマンドを打とうとして失敗
→"i" や "a" を押して挿入モードに入ったまま ":wq" を打っても、画面に文字が入力されるだけ。
Escキーでコマンドモードに戻すのが必須です。
2.":wq" などの前に大文字を入力してしまう
→ viのコマンドは大文字・小文字を区別するため、入力ミスすると「不明なコマンド」として無視されます。
実務での小技
・行番号を表示する:":set number"
編集対象の行がわかりやすくなります。
・検索:"/文字列" で下方向に検索、文字列 で上方向に検索できます。
・置換:":%s/old/new/g" でファイル全体の文字を一括置換。
これらを覚えると、viは「出られない牢獄」から「強力な作業ツール」へと変わります。
viは初見ではとっつきにくく、初心者にとっては「閉じ込められた感」が強いエディタです。
しかし、モードの概念と基本コマンドを覚えてしまえば、軽量でどこでも使える頼もしい存在になります。
「Escでコマンドモード、:wqで保存終了、:q!で破棄終了」この3つを指が覚えるまで繰り返すことが、vi脱出への第一歩です。
4. ファイルがどこいった?【findで探そう】

Linuxを使い始めた初心者が意外とよく遭遇するのが、「あれ、あのファイルどこに保存したっけ?」という状況です。
GUI(デスクトップ環境)であれば、検索窓や最近使ったファイル一覧からすぐ見つけられますが、CUI環境のサーバやターミナル作業ではそう簡単にはいきません。
そんなときに強力な味方になるのが、findコマンドです。
findコマンドの基本
findは指定したディレクトリ配下を再帰的に探し、条件に一致するファイルやディレクトリを表示してくれます。
基本形は次の通りです。

例えば、ホームディレクトリ以下からtest.txtという名前のファイルを探すなら

これで、自分のホームディレクトリ以下にあるtest.txtの場所がすぐにわかります。
大文字・小文字を区別せず探す
Linuxは大文字と小文字を区別するため、Test.txtとtest.txtは別物です。
名前の大文字・小文字を区別せず探したいときは、-inameオプションを使います。

これならTest.txtでもTEST.TXTでもヒットします。
拡張子で探す
特定の種類のファイルだけ探したい場合は、ワイルドカードを使います。

これで、/var/www配下のすべてのPHPファイルが一覧表示されます。
更新日時で探す
「最近編集したファイルを探したい」という場合は、-mtime(更新からの日数)や-mmin(分単位)を使います。

これは、過去1日以内に更新されたファイルを探します。
見つけたらすぐに中身を確認する
findの出力結果をそのまま別のコマンドに渡すこともできます。
例えば、見つけたログファイルの中から「error」という文字を含む行を探したい場合

{}は見つかったファイル名の場所に展開され、\;でコマンドの終わりを示します。
実務での活用ポイント
・サーバトラブル時、設定ファイルの場所を急いで探す
・バックアップ後に必要なファイルが正しく保存されているか確認する
・アップロードされたファイルが正しい場所に入っているか検証する
findはシンプルながら奥が深く、条件を組み合わせることでほぼ無敵の検索ツールになります。
Linuxでは、ファイルの場所がすぐに見つからないことがよくありますが、findコマンドを使えばその不安は一気に解消されます。
findを自由自在に使いこなせるようになれば、「ファイルがどこにあるかわからない」という壁は簡単に乗り越えられるでしょう。
5. インターネットにつながらない!?【ネットワーク設定の罠】

Linux初心者が意外とハマるのが「ネットに繋がらない」というトラブル。
ブラウザを開いてもページが真っ白、ping google.com を打っても返事がない…そんな経験はありませんか?
この症状、原因はさまざまですが、大きく分けると次の3つに分類できます。
1.物理的な接続不良
LANケーブルが抜けている、Wi-Fiがオフになっている、ルーターの電源が落ちている…。
まずは基本中の基本、物理的な接続を確認しましょう。意外とケーブルの緩みが原因だったというケースは多いです。
2.IPアドレスやゲートウェイの設定ミス
Linuxではネットワーク設定を手動で行うこともあります。
例えば、IPアドレスが 192.168.x.x ではなく 169.254.x.x になっていたら、DHCPでの取得に失敗しています。
ip addr コマンドや nmcli device show で現在の設定を確認しましょう。
3.DNS設定の不備
ネットワーク自体はつながっていても、名前解決ができない場合があります。
ping 8.8.8.8 は通るのに ping google.com が通らないときは、DNS設定が怪しいです。
/etc/resolv.conf の内容をチェックし、nameserver 8.8.8.8 のような正しい設定があるかを確認しましょう。
トラブルシューティングの流れ
・物理層の確認:ケーブル、Wi-Fi、ルーターをチェック
・IPアドレス確認:ip addr で異常な値がないか確認
・ルーティング確認:ip route でデフォルトゲートウェイが設定されているか確認
・DNS確認:/etc/resolv.conf と dig コマンドで動作を検証
予防のためのポイント
・DHCP任せではなく、必要に応じて固定IPを設定しておく
・ネットワークの状態を素早く確認できるコマンド(ping、traceroute、nmcli)を覚えておく
・作業前に設定ファイルのバックアップを取っておく
初心者のうちは、ネットワークエラーが出ると「サーバが壊れた!」と焦りがちですが、多くの場合は設定や接続の小さなミスです。
落ち着いて原因を切り分ければ、案外すぐに解決できます。
6. なぜsudoが必要?【管理者権限の考え方】

Linuxを使い始めてしばらくすると、コマンド実行時に「Permission denied」とは別に「operation not permitted」というエラーに遭遇することがあります。これらは単にファイルのパーミッションの問題だけでなく、「そもそもあなたにはその操作を行う権限がない」ということを示しています。ここで登場するのが sudo です。
sudu は Super User DO の略で、「一時的に管理者権限(root権限)でコマンドを実行する」ための仕組みです。Linuxでは管理者権限を持つユーザー(root)がシステム全体を制御できます。
逆に言えば、一般ユーザーは重要なファイルや設定に触れられないように制限されています。これは安全性を守るための基本的な設計思想です。
もしsudoがなかったら、rootユーザーで直接ログインし続けることになり、誤ってシステムに致命的な変更を加えてしまうリスクが高まります。
例えば、"rm -rf /" のようなコマンドを実行すれば一瞬でOSが壊れます。sudoは「必要な時だけ」「必要な操作だけ」管理者権限を使えるようにする安全弁なのです。
また、sudoを使うと操作履歴が "/var/log/secure" などに記録されます。誰がいつ管理者権限を使ったのかが追跡できるため、複数人での運用やセキュリティ監査にも有効です。
例えば、ソフトウェアのインストール時は以下のようにsudoを使います。

この時、sudoはあなたが管理者権限を使う資格があるかどうかを確認するため、パスワード入力を求めます。
成功すれば、そのコマンドだけroot権限で実行されます。
初心者が陥りやすい間違いとして「sudoを毎回付け忘れる」か「なんでもsudoを付けてしまう」の二極端があります。前者は権限不足で作業が進まず、後者はセキュリティ上危険です。大事なのは、「なぜその操作に管理者権限が必要なのか」を理解した上でsudoを使う ことです。
まとめると、sudoはLinuxの安全性と柔軟性を両立するための必須ツールです。権限の仕組みを正しく理解し、必要な時だけsudoを活用すれば、安心してシステムを運用できます。
7. 変なエラーメッセージ!【ログの読み方がわからない】

Linux初心者がつまずく最後の壁として多いのが、「エラーメッセージは出ているけれど、意味が分からない」というケースです。ターミナルやアプリケーションが何かを訴えているのに、こちらは外国語を聞かされている気分…
そんな経験はありませんか?
Linuxでは、ほとんどの動作やエラーはログファイルに記録されています。エラーの原因を突き止めるには、このログを読み解くスキルが欠かせません。たとえば、メールサーバなら "/var/log/maillog" Webサーバなら "/var/log/httpd/error_log" や "/var/log/nginx/error.log" に重要な情報が残っています。
ログの探し方と基本コマンド
まずはtailコマンドでログの末尾をリアルタイム監視します。

これで新しいログが追加されるたびに表示されるので、エラーが再現した瞬間に確認できます。
また、特定のキーワードを探すならgrepが便利です。

エラーの発生時刻がわかっている場合は、日時で絞り込むことも可能です。

英語のエラーメッセージを読むコツ
Linuxのエラーメッセージはほぼ英語ですが、難しい単語は少なく、パターン化されています。
例えば、
・Permission denied → 権限がない
・No such file or directory → 指定したファイルやディレクトリが存在しない
・Connection refused → 接続を拒否された
まずはよく出る定型句を覚えると、読むスピードが上がります。
実務でのポイント
・ログは時系列に並んでいるため、エラー直前の記録も必ず読む
・同じエラーが繰り返し出ていないか確認する
・必要に応じてログのローテーション設定(logrotate)を見直す
「よくわからないからスルー」してしまうのが一番危険です。ログはLinuxからの大事な“手紙”のようなもの。
読み方に慣れれば、問題解決までの時間が大幅に短縮されます。
怖がらずに、まずはtailやgrepで覗いてみることから始めましょう。
おわりに
Linuxを使い始めたばかりの頃は、「コマンドが動かない」「設定が反映されない」「ネットにつながらない」など、思わぬ壁にぶつかることが多いものです。でも、それは決してあなたが不器用だからではなく、誰もが通る成長のステップ。ひとつひとつのトラブルには必ず原因があり、調べて、試して、解決する過程こそが、Linuxの醍醐味でもあります。
今回紹介した7つの壁は、私自身も初心者の頃にぶつかってきたものばかりです。そして、そのたびに少しずつ知識と自信を積み重ねてきました。大事なのは「怖がらないこと」と「失敗を楽しむこと」。トラブルを解決できた瞬間の達成感は、きっとあなたのエンジニア人生を豊かにしてくれるはずです。
さあ、次に壁が現れたら、「また一歩成長できるチャンスだ!」と思って、ぜひ楽しんで乗り越えていきましょう。
GSVは企業の大切なデータを守る安全なNASサーバーシステムです。自動バックアップやRAID構成による多重保存で、データの消失リスクを最小限に抑えます。ネットワーク接続だけで社内外から安全にデータにアクセス可能で、異なるOS間でもスムーズな運用が可能です。
スケジュール管理やToDoリストの一元管理機能を備え、チームの業務効率化を支援します。契約期間中の無償アップデートで常に最新機能を利用可能です。
さらに、無停電電源装置(UPS)の標準装備、ウイルス検知システム、柔軟なアクセス制限により、物理的な障害やセキュリティリスクからも企業データを保護。GSVは安全で効率的なデータ管理環境を提供します。
【関連記事】