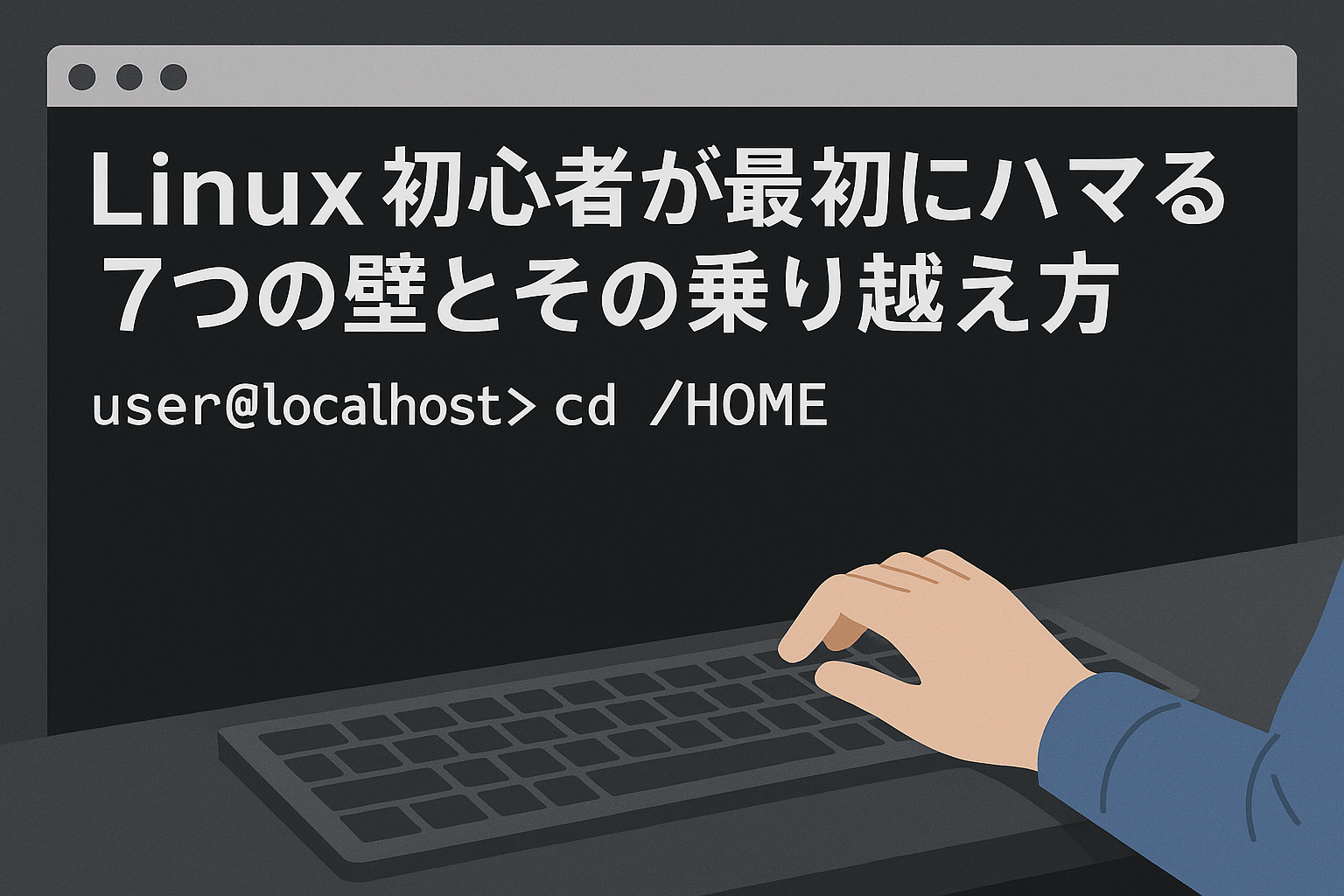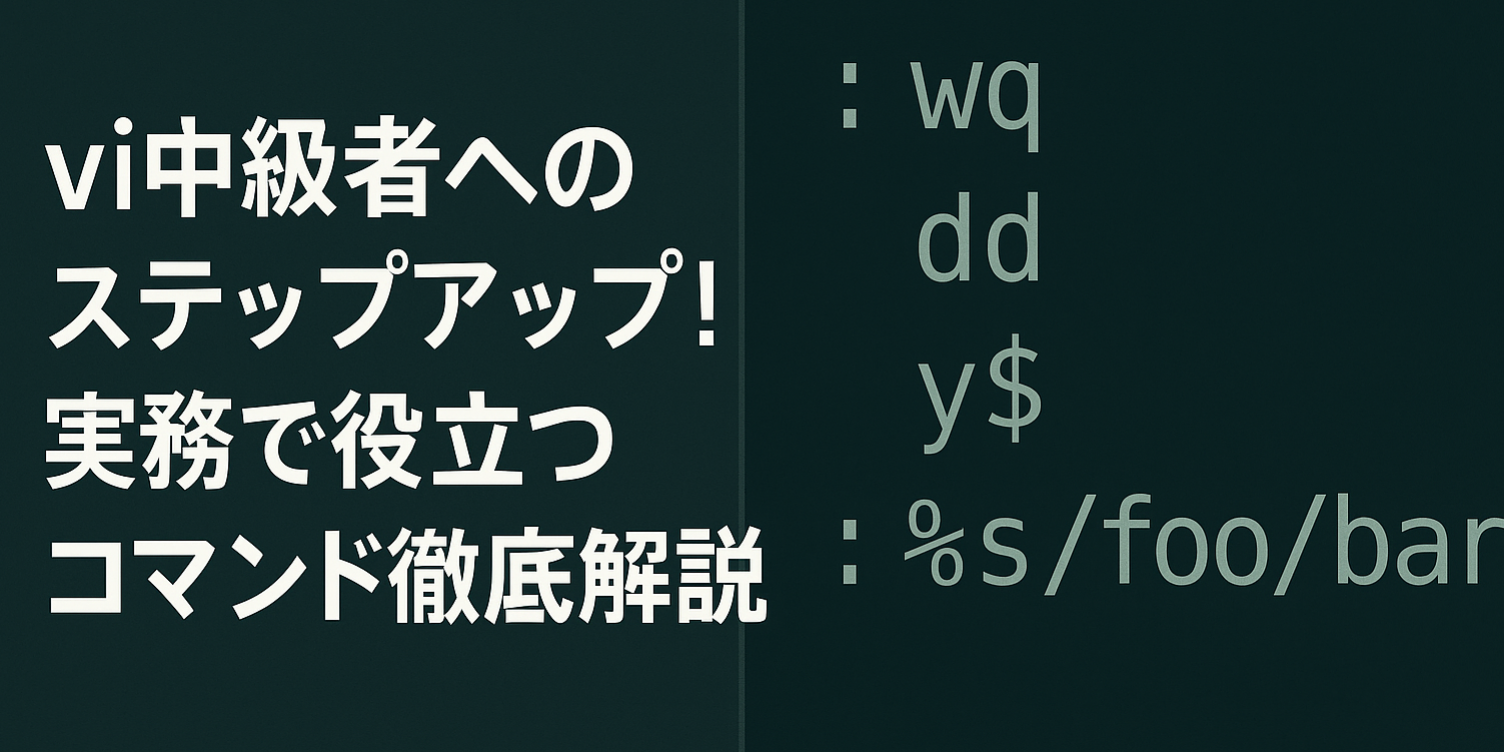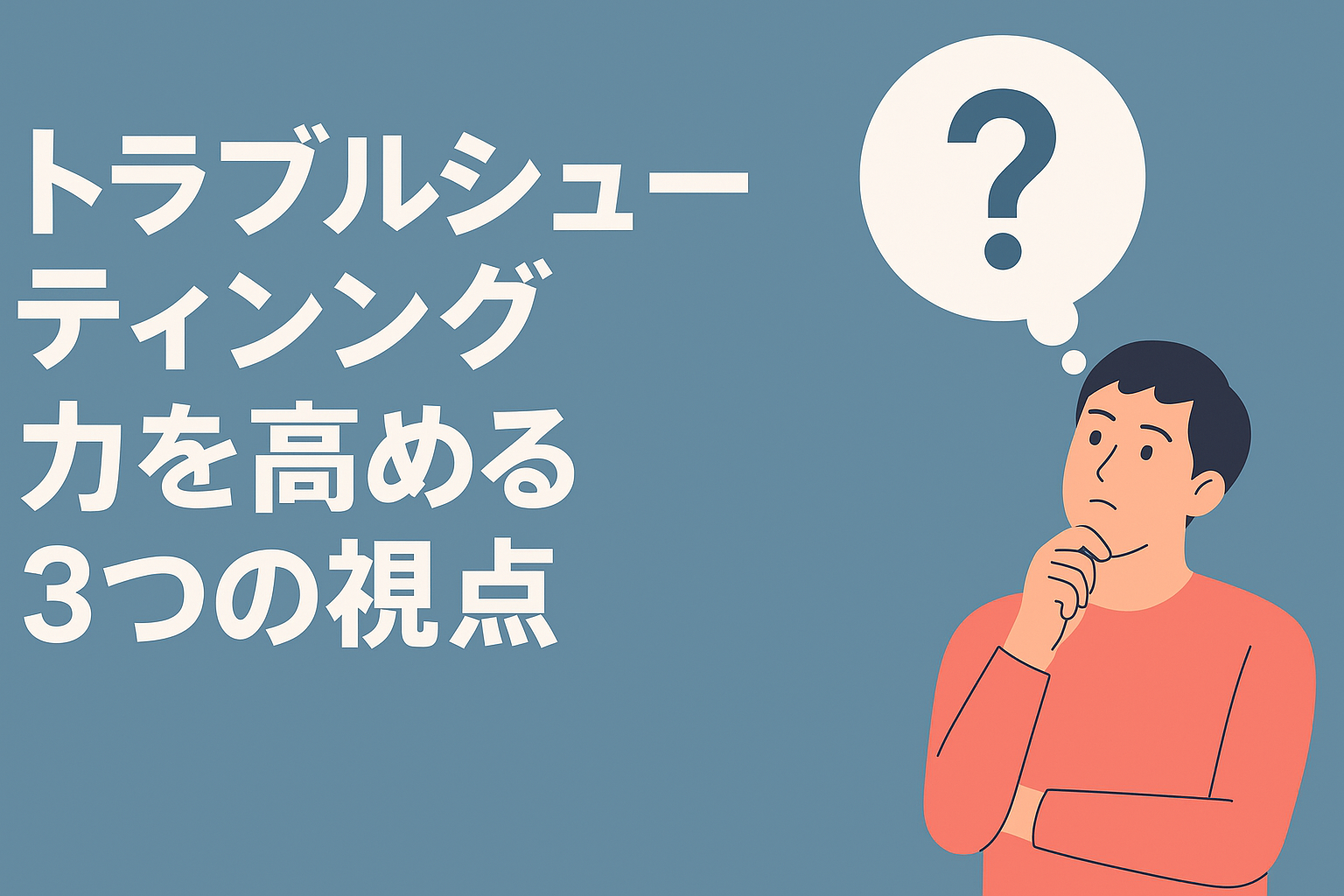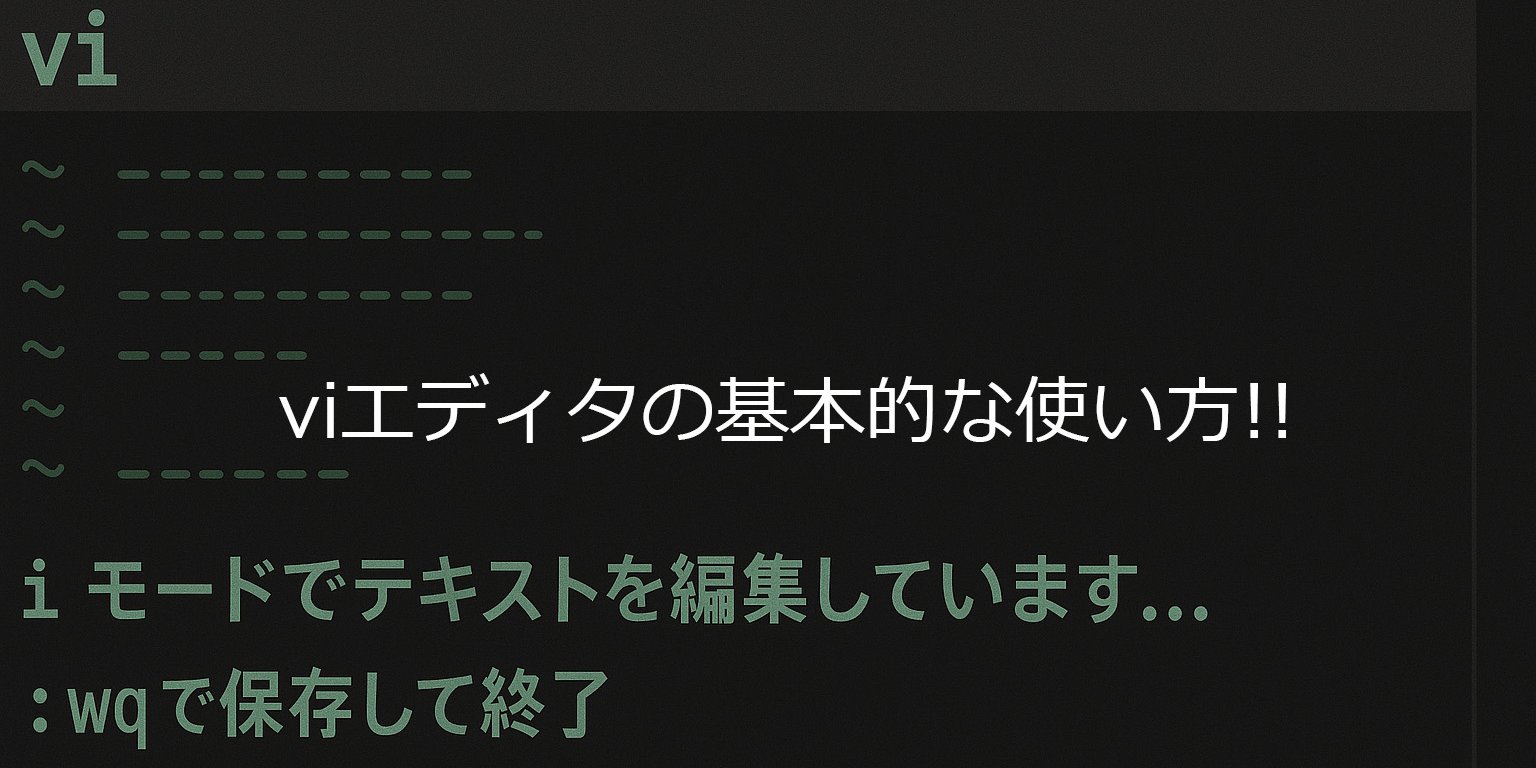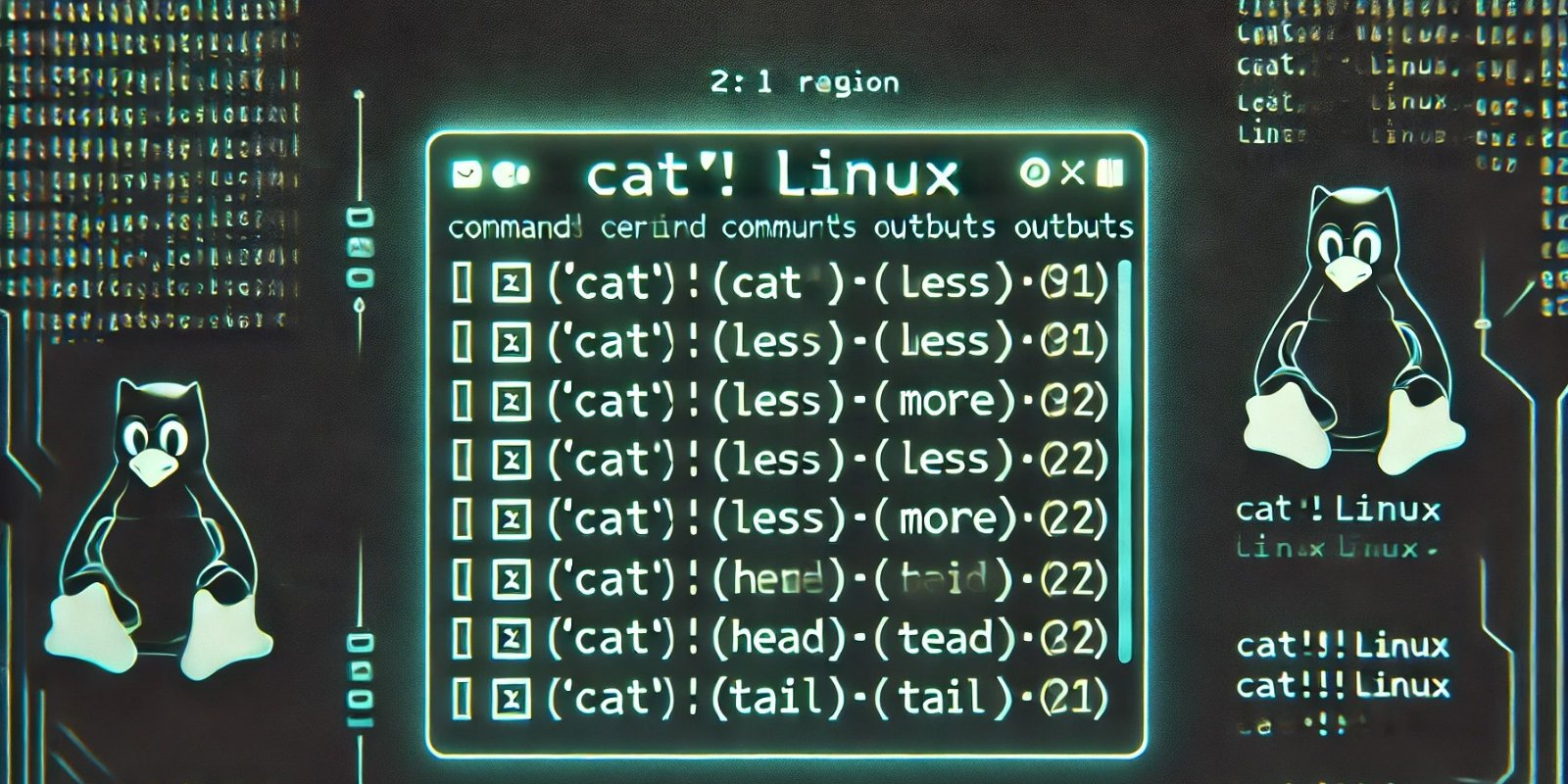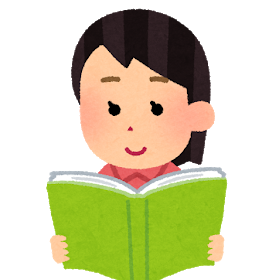株式会社グローバルゲート公式ブログ
人に話したくなるPCの裏側 :電源ボタンを押した瞬間、PCの中で何が起きているのか
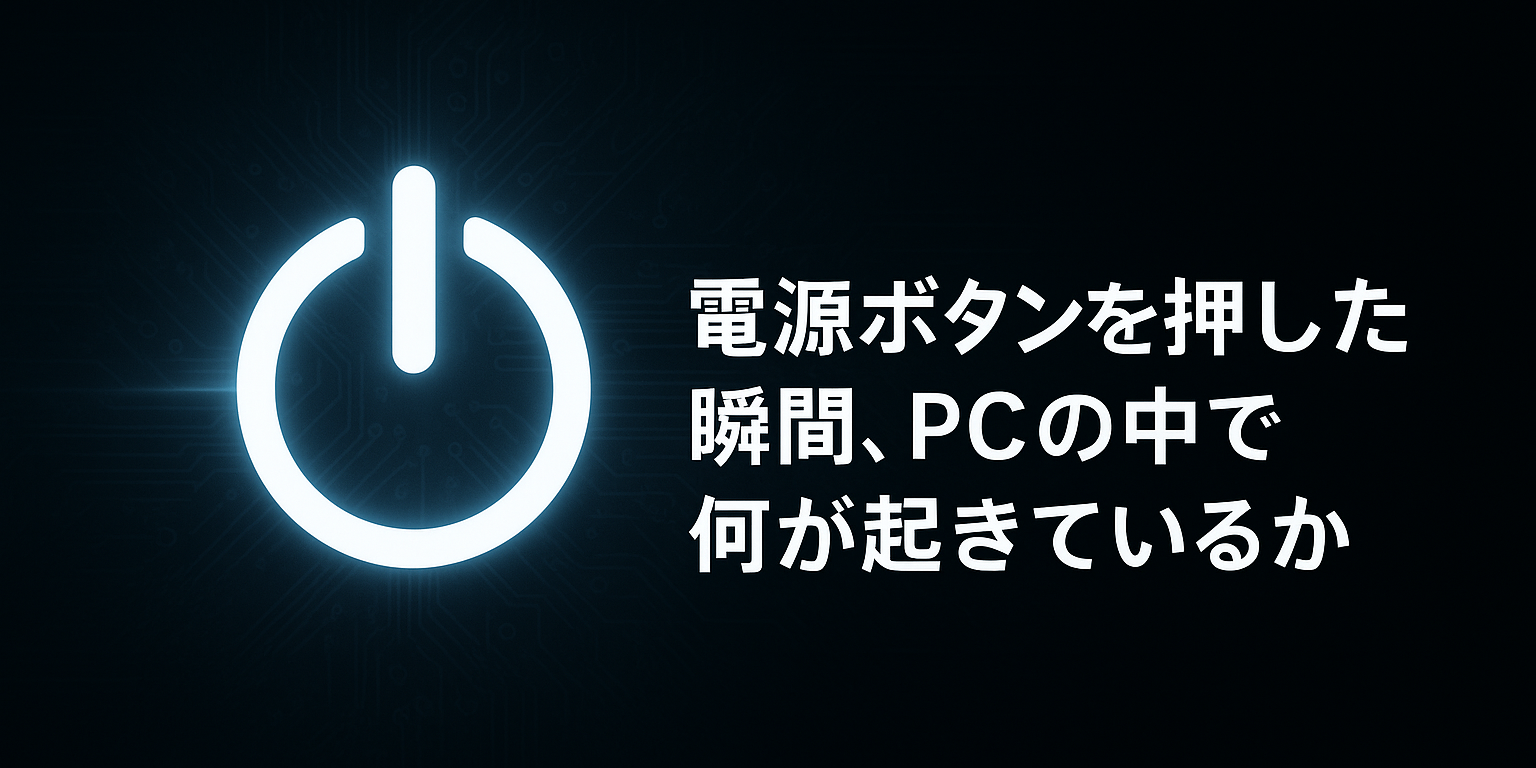
こんにちは!株式会社グローバルゲートでサーバ管理をしてるタカです。
普段、私たちは何気なくパソコンの電源ボタンを押しています。仕事を始めるとき、趣味の動画を見たいとき、あるいはメールをチェックしたいとき。ボタンを「ポチッ」と押せば、数十秒後には見慣れた画面が立ち上がり、いつものように使えるようになります。けれど、その短い時間のあいだにパソコンの中では、実はとても複雑で面白いドラマが展開されているのです。
「電源を入れるとパソコンが起動する」当たり前すぎて、わざわざ考えたことがない人も多いかもしれません。でも、裏側をのぞいてみると、パソコンという機械がどれだけ緻密に動いているかがわかり、思わず誰かに話したくなるはずです。
たとえば人間に例えるなら、電源ボタンは「目覚まし時計」。眠っていた体にスイッチが入り、血がめぐり始める瞬間です。次に「体調チェック」が行われます。ちゃんと手足は動くか、目は見えるか、耳は聞こえるか、そんな確認をしてからようやく「今日の予定は何だったっけ?」と頭の中でスケジュールを探し始めます。そして準備が整ったら、一日の始まりを告げる朝礼のように「さあ、仕事を始めよう!」とスタートするのです。
パソコンの世界でも同じことが起きています。電気が流れ、部品が正しく働けるか確認され、起動に必要なプログラムが探され、そしてようやく画面にロゴが映し出されます。その一連の流れはわずか数十秒ですが、舞台裏では何段階ものチェックと準備が行われているのです。
この記事では、電源ボタンを押してからログイン画面が出るまでの裏側を、専門用語をなるべく使わずに、イメージしやすいストーリーとして紹介します。難しい仕組みを覚える必要はありません。「へえ、こんなことが起きているんだ!」とちょっと驚いてもらえれば、それで十分です。次にパソコンを立ち上げるとき、ほんの少し違った目でその時間を楽しめるようになるかもしれません。
はじめに: 電源ボタン一押しの裏側で何が起きてる?

毎日使っているパソコン。スイッチを押せば当たり前のように画面が光り、数十秒後には使えるようになります。けれど「電源ボタンを押した瞬間」に、いったいパソコンの中では何が起きているのでしょうか?
実はその時間、パソコンの内部では「起床→健康診断→今日の予定を確認→仕事を開始」という一連の流れがものすごい速さで行われています。人間で言えば、目覚ましで目を覚ました瞬間に体をチェックし、忘れ物がないか確認してから出勤するようなもので、 最初に行われるのは「目覚め」です。電気が流れ、部品たちが目を覚まし、準備を始めます。次に「体調チェック」が始まります。メモリやハードディスク、キーボードやマウスなど、必要なパーツがきちんと動けるかどうか確認しているのです。もし不具合があれば、画面にエラーメッセージを出したり、ビープ音で知らせてくれることもあります。
問題がなければ「今日の仕事は何だったかな?」という段階へ。ここでパソコンは、保存されている“仕事の台本”を探し出します。その台本こそが、みなさんが使っているOS(WindowsやmacOS、Linuxなど)です。台本を見つけたら「さあ、進行開始!」と合図を送り、各部品に役割を振り分けていきます。CPUは司令塔として命令を出し、メモリは作業スペースを整え、ストレージは必要な道具を倉庫から取り出すそんなチームワークで一斉に動き出すのです。
そして最後に、いよいよ「舞台の幕」が上がります。画面にロゴやロード画面が表示され、やがてログイン画面へ。これでパソコンは「仕事をする準備が整いました」と伝えているのです。
わずか十数秒の間に、これだけのやり取りが裏で行われていると知ると、次にパソコンを起動するときに少し違った気持ちになるかもしれません。「今ごろパソコンの中で健康診断をしてるんだな」と想像すると、ちょっと愛着がわいてくるはずです。
全体像を一枚で(図解):起動の流れマップ

電源ボタンを押してからログイン画面が出るまで、パソコンの中ではいくつものステップが流れるように進んでいきます。個別に見ると難しく感じるかもしれませんが、まずは全体の流れを一枚のマップとして眺めると、とても理解しやすくなります。
ここでは、専門用語をできるだけ避け、シンプルな流れにまとめました。大きく分けると「電源投入」「自己チェック」「OSの呼び出し」「サービス準備」「ログイン画面」の5段階です。
1.電源投入
電源ボタンが押されると、電気がマザーボードに流れ、各部品が「おはよう」と目を覚まします。まだ作業は始まっていませんが、体に血が巡り始める瞬間です。
2.自己チェック
次に「体調チェック」にあたる自己診断が始まります。メモリ、ストレージ、キーボード、マウスなどが正しく動けるかどうかを確認します。もし異常があればエラー画面やビープ音で知らせてくれる仕組みです。
3.OSの呼び出し
問題がなければ、いよいよ本題。「今日の仕事はどこにある?」とパソコンは探し始めます。ストレージに保存されているOSを見つけ出し、そのスタート地点を呼び出します。ここが「仕事の台本」を手に取る瞬間です。
4.サービス準備
OSが立ち上がると、CPUやメモリ、ストレージなどに役割が割り振られ、必要な道具が揃えられていきます。人間で言えば、出勤して机の上に資料を広げる場面に似ています。ネットワークや画面表示の準備もこの段階で行われます。
5.ログイン画面
最後に「受付」にあたるログイン画面が表示されます。社員証や名札を見せるように、ユーザーが名前とパスワードを入力し、本人確認が完了すれば準備は完了。いよいよ作業を始められるわけです。
こうして見ると、ただ「スイッチを押してから数十秒」と思っていた時間が、実は段階ごとにきれいに整理された流れで進んでいることがわかります。頭の中でイメージマップを描いておくと、このあとの細かい仕組みを学ぶときも理解がスッと入ってくるはずです。
次回以降の記事では、この5段階をひとつずつ深掘りしていきますが、まずは「大まかな地図」を持っておくことが大切です。迷子にならずに記事を読み進められる、いわばナビゲーションの役割を果たしてくれるからです。
電気が走る:電源ユニット→マザーボード→CPU/メモリ

電源ボタンを押すと、最初に働き出すのが「電源ユニット」と呼ばれる装置です。コンセントから送られてくる電気を、そのまま部品に流すことはできません。なぜなら、パソコンの各部品はとても繊細で、必要な電圧や電流がバラバラだからです。そこで電源ユニットは「電気の調整役」として、部品ごとにちょうどいい形に電気を分けてあげます。まるで家庭の分電盤が、コンセントや照明、エアコンなどに電気を安全に分けているのと同じ仕組みです。
調整された電気は、マザーボードへと流れ込みます。マザーボードはパソコンの「道路網」や「司令室」にあたる場所で、電気だけでなく信号やデータも行き来する大きな基盤です。ここから各部品へとエネルギーが行き渡り、パソコンが目を覚ましていきます。
まず電気を受け取るのはCPU(中央処理装置)です。CPUは「パソコンの頭脳」と呼ばれる存在で、電気が流れ込むことで動き出します。ちょうど人間の脳に酸素が届いて活動を始めるようなイメージです。CPUが元気に動くことで、これから先に行う数えきれない命令処理が可能になります。
同時に電気はメモリにも流れます。メモリは「作業机」のような場所で、ここが暗いままでは作業を始めることができません。電気が供給されることでメモリは「机の電気スタンドが点いた状態」になり、いつでも作業用のデータを広げられる準備が整います。
つまり、電源ユニット→マザーボード→CPU/メモリという流れは、パソコンにとっての「血液循環」とも言える大事なプロセスなのです。電気が流れなければどんな部品も働けません。逆に、正しく流れた瞬間から部品たちは一斉に目を覚まし、次の「体調チェック」や「OS起動」に備えることができるのです。
わずか一瞬の出来事ですが、この「電気が走る」ステップがなければパソコンはまったく動き出せません。まるで、人間が朝に心臓から血液を送り出して全身が活動を始めるように、パソコンも電気が全身を駆け巡ることで生命を得るのです。
目覚めの司令塔:BIOS/UEFIとは

電源が流れ、CPUやメモリが目を覚ましたら、次に登場するのが BIOS や UEFI と呼ばれるプログラムです。これはパソコンにとって「目覚めの司令塔」のような存在。すべての部品が正しく働けるかを点検し、起動の順番を指揮する役割を担っています。
BIOS(バイオス)は古くから使われてきた仕組みで、今のパソコンでは改良版であるUEFI(ユーイーエフアイ)が主流になっています。呼び方は違っても、役割はどちらも同じ。「まだ眠気の残る部品たちに朝礼を開いて、今日の予定を伝えるリーダー」だと考えるとわかりやすいかもしれません。
朝礼でまず行うのは「体調チェック」です。これは POST(Power-On Self Test) と呼ばれる動作で、メモリがちゃんと動いているか、キーボードやマウスが使えるか、ストレージが応答するかなどを確認します。もし異常があれば、画面にエラーメッセージを表示したり「ピッ、ピッ」というビープ音で知らせてくれます。これが、司令塔からの「誰か体調不良はいないか?」という点呼なのです。
チェックが終われば、次は「今日の仕事の台本」を探します。つまり、どのストレージにOSが入っているかを調べ、そこから起動の準備を始めるのです。もしUSBメモリやDVDから起動する設定にしていれば、そこを優先的に探してくれます。この「探す順番」を決めるのもBIOS/UEFIの大事な役割。まさに司令塔が「まずはこの場所を見に行け」と指示しているイメージです。
さらにUEFIでは、古いBIOSにはなかった便利な機能も用意されています。グラフィカルな画面でマウス操作ができたり、大容量のハードディスクからも起動できたりと、現代的な使い勝手が加わっています。昔ながらの紙の掲示板から、デジタルサイネージに変わったようなものですね。
つまり、BIOS/UEFIがいなければパソコンは次に進むことができません。どんなに優秀なCPUや大容量のメモリがあっても、誰かが全体を仕切らなければバラバラに動いてしまうからです。司令塔が合図を出してはじめて、パソコン全体が「同じ方向」に向かって動き出せるのです。
わずか数秒で終わるプロセスですが、その裏では部品一つひとつがきちんと点呼され、行進の準備を整えている。そう考えると、起動時にロゴ画面が出るあの時間が、ちょっと頼もしく感じられるかもしれません。
起動先を決める:ブート順序とブートデバイス

BIOSやUEFIが体調チェックを終えたら、次に大事なのは「どこからパソコンを起動するか」を決めることです。この仕組みを ブート順序 と呼びます。
パソコンは、電源を入れたらすぐにOSを読み込まなければ動きません。しかしOSはCPUやメモリの中に最初から入っているわけではなく、必ずどこかのストレージに保存されています。そこでBIOS/UEFIは「今日はどの部屋にOSがあるのか?」と探しにいくわけです。
例えるなら、出勤前に「今日の仕事の資料は机の上?ロッカー?それともUSBメモリ?」と確認しているようなもの。もし正しい場所を見つけられなければ、パソコンは「起動できません」というエラーを出して止まってしまいます。
一般的なパソコンでは、ブート順序は次のように設定されていることが多いです。
1.USBメモリやDVDドライブ
2.ハードディスクやSSD(普段OSが入っている場所)
3.ネットワーク(会社や学校で使われることがある特殊な起動方法)
この順番に沿ってBIOS/UEFIは「ここにOSはあるかな?」と確認していきます。例えばUSBメモリを差しておけば、まずそこを調べてOSが見つかればUSBから起動します。なければ次のハードディスクを調べる、という流れです。
この仕組みのおかげで、OSをインストールするときにUSBメモリから起動したり、修復用のDVDから立ち上げたりできるのです。逆に、うっかりUSBメモリを差しっぱなしにしていると、思わぬ画面が出て戸惑うのも、このブート順序のせいだったりします。
初心者にとっては難しく聞こえるかもしれませんが、要は「パソコンは、どの部屋にOSがあるか順番に探す」というだけのこと。順序はBIOS/UEFIの設定画面で自由に変えられるので、普段はSSDから直接起動するようにしておき、必要なときだけUSBを優先する、といった使い分けができます。
つまりブート順序は、パソコンにとっての「地図」や「スケジュール表」のようなもの。正しく設定してあげれば、迷子になることなくスムーズにOSを呼び出してくれるのです。
小さな主役:ブートローダー

パソコンの電源を入れると、BIOSやUEFIが体調チェックを終え、どのデバイスから起動するかを決めます。するといよいよ次に登場するのが「ブートローダー」と呼ばれる小さなプログラムです。名前は少し難しそうに聞こえますが、役割はとてもシンプル。OSを呼び出して舞台に登場させる“案内役” なのです。
イメージとしては、演劇の舞台裏にいる「影の案内人」。スポットライトを当てる前に、「次は主役の登場です!」と呼び込む役割を果たしています。パソコンの世界では、主役はもちろんOS(WindowsやLinux、macOSなど)。ブートローダーが正しく働いてくれないと、OSは出番を迎えられません。
ブートローダーは、パソコンのストレージの「とても小さな領域」に置かれています。たとえば古い方式では「MBR(マスターブートレコード)」、新しい方式では「EFIシステムパーティション」と呼ばれる場所でサイズはほんの数百キロバイト程度と、とても小さいのに、役割は極めて重要です。
具体的に何をしているかというと、まず「OSをどこから読み込むのか」を決定し、OSの核となる部分(カーネル)をメモリに展開して「さあ、ここからはあなたの出番です」とバトンを渡すのです。この瞬間を境に、パソコンの制御はBIOS/UEFIからOSへと切り替わります。
この仕組みのおかげで、私たちは複数のOSを使い分けることもできます。たとえばWindowsとLinuxを1台のPCにインストールしておけば、ブートローダーの画面で「今日はどっちを使う?」と選ぶことができるのです。これを デュアルブート と呼び、技術者やPC好きにはおなじみの機能!
普段、一般ユーザーがブートローダーの存在を意識することはあまりありません。しかし、もし壊れてしまうとどうなるでしょうか?答えはシンプルで、OSが立ち上がらなくなってしまいます。まるで舞台袖の案内人が欠けてしまい、主役が舞台に出てこれなくなるようなものです。そのためブートローダーは小さいながらも、まさに「小さな主役」と呼ぶにふさわしい存在なのです。
次にパソコンを起動するとき、ほんの数秒の間に「小さな案内人」が舞台裏で働いていることを思い浮かべると、いつもより少し愛着を持って眺められるかもしれません。
いよいよOS:カーネル読み込みとドライバ準備

ブートローダーがOSを呼び出すと、いよいよパソコンの「本番ステージ」が始まります。ここで登場するのが カーネル と呼ばれる存在です。カーネルはOSの中核部分で、すべての部品に指示を出す「総監督」のような役割を持っています。
カーネルが読み込まれると、まずはパソコンを動かすために欠かせない最低限の準備が行われます。たとえば「メモリをどう使うか」「CPUにどう命令を送るか」といった基本的な取り決めがここで決まります。これはまるで舞台監督が、照明係や音響係に「まずはここから動いて」と最初の指示を出すような場面です。
次に必要になるのが ドライバ の読み込みです。ドライバとは、ハードウェアとOSをつなぐ通訳のような存在。キーボードやマウス、ディスプレイ、ネットワークカードなどは、それぞれ「自分専用の言葉」でしか話せません。そのままではOSは理解できないため、ドライバが「翻訳者」として間に入り、「この人はこういう風に動きたいと言ってます」と伝えてくれるのです。
たとえば、USBメモリを差し込んだときにすぐに使えるのも、適切なドライバが働いているからです。もしドライバがなければ、せっかくの機器も無言のまま。まるで舞台に役者が来ても、通訳がいないせいで台詞が伝わらない状態になってしまいます。
この「カーネルとドライバの準備」がしっかり整うことで、パソコンは初めて「全員が同じ舞台で会話できる」状態になります。ここまで来ると、画面にはロゴや進捗バーが表示され、ユーザーも「起動してるな」と安心できる瞬間になるのです。
つまりこのステップは、パソコンが単なる箱から「人が使える道具」へと変わる大きなターニングポイント。カーネルが指揮を執り、ドライバが橋渡しをすることで、CPUもメモリもストレージも「同じチーム」として動き出すのです。
わずか数秒の出来事ですが、その裏には綿密な役割分担と連携が存在しています。次にパソコンを立ち上げるときは、「今ごろカーネルが合図を出して、ドライバが走り回ってるんだな」と想像してみると、ちょっと面白い気持ちになるかもしれません。
サービス起動の舞台裏:Winlogon / Service Control Manager と systemd

カーネルとドライバが準備を整えたら、いよいよパソコンは「実際に働くためのサービス」を動かし始めます。サービスとは、ユーザーが気づかないところで裏方として働いているプログラムのこと。ネットワーク接続やセキュリティ、音声の再生やプリンタ管理など、日常的に使う機能を支えるために欠かせません。
ここから先の流れは、WindowsとLinuxで少し違います。それぞれの世界の「舞台裏」を見てみましょう。
Windowsの舞台裏
Windowsでは、まず Winlogon(ウィンログオン) というプログラムが登場します。名前の通り「ログイン」を受け持つ役者です。ユーザー名とパスワードを入力すると、このWinlogonが「本人かどうか」を確認し、問題なければデスクトップを表示します。
ログインが済むと、次に Service Control Manager(サービス制御マネージャ) が裏方として動きます。これは「各サービスの舞台監督」のような存在です。ネットワークを有効にしたり、セキュリティ関連のサービスを立ち上げたり、バックグラウンドで動く無数のプログラムを順番に起動していきます。もしこれがいなければ、ユーザーはインターネットに接続できず、印刷も音楽再生もできなくなってしまいます。
Linuxの舞台裏
一方Linuxでは、systemd(システムディー) という仕組みが同じ役割を果たします。systemdは「サービスの起動順序を管理する総監督」で、ネットワーク、ログ管理、タイマーなどを一斉に動かしていきます。Linuxはサーバーでも多く使われているので、このsystemdの効率の良さはとても重要です。
systemdの特徴は、サービスを「並列」に起動できること。たとえばネットワークの準備とログ管理を同時に進める、といった動きが可能です。そのおかげで起動時間を短縮でき、パソコンはより早くユーザーを迎え入れることができるのです。
WindowsでもLinuxでも、この段階は「裏方のスタッフが一斉に持ち場につく瞬間」です。表舞台に出るのはデスクトップやログイン画面ですが、その裏では無数のサービスが協力して環境を整えています。
次にパソコンを起動したときには、ログイン画面が出るまでの間に「Winlogonやsystemdが裏方で走り回ってるんだな」と想像してみてください。ちょっと舞台裏を覗いたような気分になれるはずです。
ようこそ!ログイン画面が出るまで

ここまでで、電源が入り、体調チェックが済み、ブートローダーがOSを呼び出し、カーネルとドライバが準備を整え、サービスが次々と動き始める そんな舞台裏を見てきました。そして、いよいよ最後のステップが「ログイン画面の表示」です。
ログイン画面は、言わば 「舞台の幕が上がる瞬間」。ここから先はユーザーが主役として登場する場面です。裏方の準備がどれだけ整っていても、この画面が表示されなければ、パソコンはまだ「観客を迎え入れる前」の状態。まさにクライマックスと言える瞬間なのです。
Windowsの場合は、Winlogon が中心となって「ユーザーを迎え入れる受付」として働きます。入力されたユーザー名やパスワードをチェックし、本人確認が取れれば、デスクトップ環境を整えてユーザーを案内します。まるで劇場の入り口でチケットを確認して「どうぞ、こちらへ」と席へ案内する係員のようです。
Linuxの場合は、環境によって少し違いがあります。サーバー用途では黒い画面にログインを促すテキストベースの受付が出ますし、デスクトップ環境では ディスプレイマネージャ と呼ばれるプログラムが登場します。これは華やかな受付係のようなもので、ユーザーごとに用意されたデスクトップ環境へとスムーズに案内してくれます。
この「ログイン画面が出る」までには、見えないところで多くの仕組みが連携しています。
画面表示のためのグラフィックドライバ
キーボードやマウスの入力を受け取る仕組み
ネットワークやセキュリティの初期化?どれか一つでも欠けてしまえば、ログイン画面は正しく表示できません。まさに裏方スタッフ総出で作り上げる総合演出なのです。
そして、ログイン画面が現れた瞬間、パソコンは「準備完了!」と声をあげています。ここからはユーザーが入力する番。本人確認が終われば、いよいよデスクトップが姿を現し、私たちはアプリを開き、ファイルを操作し、ネットにつなぐことができます。
つまり、ログイン画面は「裏方から表舞台への切り替え」を象徴する存在。パソコンが単なる機械から「あなた専用の環境」へと変わる決定的な瞬間なのです。次にパソコンを起動したとき、あの当たり前に見える画面の裏側に、たくさんの働きが詰まっていることを思い出してみてください。きっと少し特別に感じられるはずです。
まとめ
今回は「電源ボタンを押した瞬間からログイン画面が出るまで」の裏側を、流れに沿って一つずつ見てきました。普段は数十秒で終わってしまうこの時間の中で、実は多くの仕組みが段階的に働いています。
最初に電気が部品を目覚めさせ、BIOS/UEFIが体調チェックを実施。次にブート順序を確認してブートローダーがOSを呼び込み、カーネルとドライバが舞台を整えます。その後、サービスが次々と起動し、最後にログイン画面という「表舞台」が現れるのです。
こうしてみると、パソコンの起動はまるで一つの舞台公演。裏方が息を合わせて働くことで、ユーザーという主役を迎え入れる準備が整います。次に電源を入れるときには、ほんの一瞬の間に繰り広げられるこの「小さな物語」を思い出してみてください。きっと、これまでより少し特別な視点でパソコンを眺められるはずです。
GSVは企業の大切なデータを守る安全なNASサーバーシステムです。自動バックアップやRAID構成による多重保存で、データの消失リスクを最小限に抑えます。ネットワーク接続だけで社内外から安全にデータにアクセス可能で、異なるOS間でもスムーズな運用が可能です。
スケジュール管理やToDoリストの一元管理機能を備え、チームの業務効率化を支援します。契約期間中の無償アップデートで常に最新機能を利用可能です。
さらに、無停電電源装置(UPS)の標準装備、ウイルス検知システム、柔軟なアクセス制限により、物理的な障害やセキュリティリスクからも企業データを保護。GSVは安全で効率的なデータ管理環境を提供します。
【関連記事】