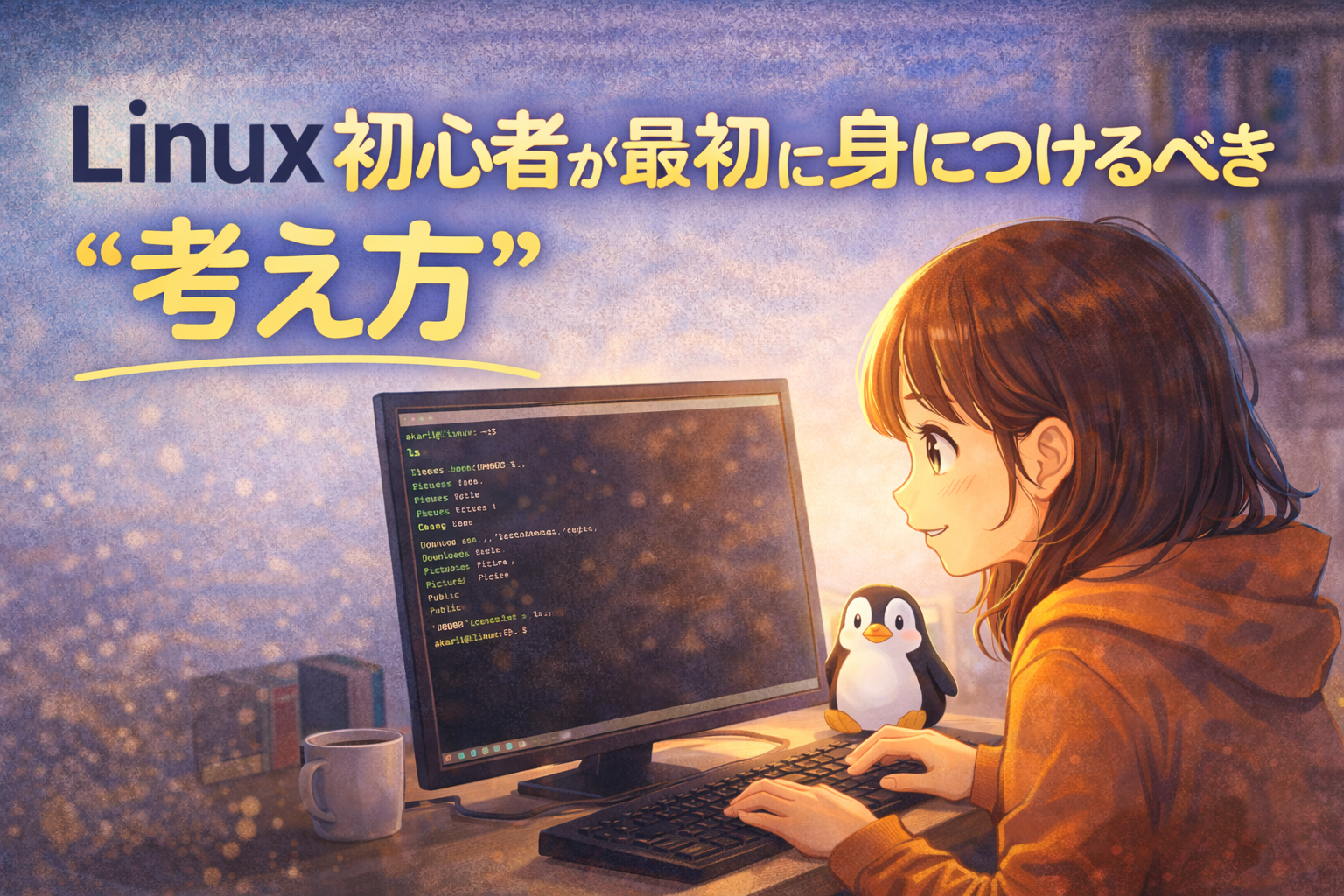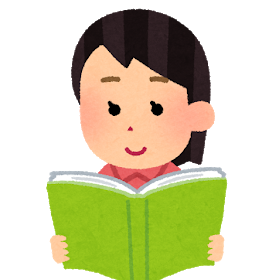株式会社グローバルゲート公式ブログ
「はじめてのマクロ撮影ガイド」世界を拡大してみよう~NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S編~

こんにちは!株式会社グローバルゲートでサーバ管理をしてるタカです。
私たちが普段、当たり前のように見ている花や身近な小物も、マクロレンズを通して覗いてみると驚くほど新しい世界が広がります。花びらの縁に並んだ繊細な産毛のような質感や、花芯に隠された複雑な模様、ガラスや金属に映り込む小さな光。肉眼では気づかないほどの細部が、写真として浮かび上がった瞬間、「こんな世界があったのか」と感動させられます。
今回、私が購入したレンズは、Nikon Z マウント用のマクロレンズ NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S。
僕自身、このレンズを手にしたことで、これまで見過ごしていたディテールに新鮮な驚きを覚え、ファインダーを覗くたびに身の回りのありふれたものがまるでアート作品のように姿を変えていきます。
今回は、このレンズの特徴やマクロ撮影の基本、そして実際に撮った作例を交えながら、初心者の方にも「世界を拡大する楽しさ」を感じてもらえるようにまとめました。
NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR Sの特徴
マクロ撮影における代表的な一本といえば、この NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S。ZマウントのS-Lineに属する高性能なマクロレンズで、実際に使ってみると「マクロの世界を本気で楽しむためのレンズ」という印象を強く受けました。ここでは僕が実際に撮影して感じた、このレンズの特徴を紹介していきます。
・等倍撮影(1:1)ができる
このレンズの大きな魅力は、被写体を 等倍(1:1) で撮影できることです。つまり、撮像素子(フルサイズなら36×24mm)の上に、実際の被写体を同じ大きさで写し出せるということ。花びらの上にのった露の粒や、蝶の羽の鱗粉の細かさまで、肉眼では見落とすようなディテールをしっかり切り取れます。普段のレンズでは「ただの点」にしか見えないものが、このレンズを通すと「立体的な世界」として現れる瞬間は、本当に感動ものです。
・VR(手ブレ補正)と解像感
マクロ撮影では「ちょっとしたブレ」が大きく写ってしまうため、手ブレ補正の有無は非常に重要です。
このレンズには VR(Vibration Reduction:手ブレ補正機能) が搭載されていて、実際に手持ち撮影でも安心感がありました。特に花の撮影など、屋外で三脚を使わずにサッと構えるときには大きな助けになります。解像感についても、さすがS-Lineといえる描写力。中心部のシャープさはもちろん、周辺までしっかり解像していて「細部まで記録する」というマクロの特性と見事に噛み合っています。撮った写真を拡大表示したときに、細部までしっかり写っていると「このレンズにしてよかった」と思わせてくれます。
・開放f/2.8による背景ボケ
マクロ撮影はどうしても「被写界深度が極端に浅い」世界です。開放f/2.8で撮影すると、ピントが合った部分は極めてシャープに写りながら、その前後は大きくボケてとろけるような描写になります。これによって、被写体の存在感を強調できるのが大きな魅力です。花びらの縁だけにピントを合わせて、背景を美しい玉ボケにすると、ありふれた花も一気に主役へと変わります。逆に少し絞り込んでf/8やf/11くらいに設定すると、細部までしっかり描写されるので「観察写真」としても成立します。表現の幅が広がるのも、このレンズの楽しさのひとつです。
・実際に使ってみて良かった点・気になった点
僕自身がこのレンズを使って特に良かったと感じたのは、解像感とボケのバランスです。花のマクロ撮影では、ディテールを残しつつも背景は柔らかくボケてくれるので、主題がとても際立ちます。また、105mmという焦点距離はワーキングディスタンス(被写体との距離)が比較的長めに取れるため、昆虫などを驚かせずに撮れるのも大きな利点です。
一方で気になったのは、やはり「被写界深度の浅さ」。開放f/2.8で撮ると数ミリ単位でしかピントが合わないことも多く、思ったよりピント合わせに苦労しました。AFは優秀ですが、状況によってはマニュアルフォーカスでじっくり追い込む必要があります。また、VRは確かに助けになりますが、極端に近接した撮影では「わずかな前後の揺れ」でもピントが外れてしまうことがあり、三脚やレリーズを使った方が確実だと感じました。
総じて、NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR Sは「細部を鮮明に描きながら、背景を美しくボカして主題を浮かび上がらせる」というマクロ撮影の醍醐味をしっかり楽しめる一本です。初心者が「マクロって面白い!」と感じるきっかけになり、中級以上のフォトグラファーにとっても表現の幅を広げてくれる、まさに万能なマクロレンズだといえるでしょう。
マクロ撮影の基本テクニック

マクロ撮影は、普段のスナップや風景写真とはまったく違う難しさと面白さがあります。被写体との距離が近いぶん、ちょっとした手ブレやピントのズレが大きく写ってしまうため、安定した撮影と正確なピント合わせが何より大切です。ここでは、初心者の方がつまずきやすいポイントを中心に、僕自身の体験を交えて基本テクニックを紹介します。
三脚 or 手持ち撮影のコツ
マクロ撮影の理想はやはり三脚を使った撮影です。被写体が動かない花や小物であれば、三脚でカメラを固定し、じっくりと構図を決めながら撮影すると成功率がぐっと上がります。特に屋内撮影や風の少ない環境では、三脚に加えてレリーズやセルフタイマーを活用するとシャッターを押すときのブレも防げます。
ただし、屋外で昆虫や風に揺れる花を狙うときには、手持ち撮影の機動力も必要です。その場合は体全体を安定させる工夫がポイントになります。肘を体に軽く固定したり、片膝を立てて腕を支えるようにしたりするだけでも安定度は大きく変わります。さらに、息を吐きながらシャッターを切るとブレが減り、よりシャープな写真が得られます。
ピント合わせ(MF/AFの使い分け)
マクロ撮影で最も悩ましいのがピント合わせです。被写界深度が浅いため、オートフォーカスに任せても思った部分に合ってくれないことが多々あります。僕の経験では、花の雄しべや昆虫の目など「ここに合わせたい」という明確なポイントがある場合、MF(マニュアルフォーカス) でじっくり追い込む方が確実です。Zシリーズには「フォーカスピーキング」や「拡大表示」があるので、MFと組み合わせるとピントの山がつかみやすくなります。
一方、AFが役立つ場面もあります。例えば昆虫が素早く動き回るときや、屋外で時間をかけられないときは、AF-C(コンティニュアスAF)を活用してある程度追従させるのも有効です。状況に応じてMFとAFを切り替える柔軟さが、マクロ撮影を楽しむコツだと感じています。
被写界深度が極端に浅いときの工夫
マクロ撮影では、f/2.8など開放で撮影するとほんの数ミリしかピントが合わず、花びらの縁にだけピントが合って他はボケてしまうことがよくあります。これは美しいボケを生かせる一方で、狙った部分をしっかり見せたいときには難点にもなります。
そんなときは、絞りをf/8やf/11程度まで絞るのが基本的な解決法です。被写界深度が広がり、被写体全体にピントが行き渡りやすくなります。ただし、絞ることでシャッタースピードが遅くなり、ブレや被写体の動きが写り込む可能性があるので注意が必要です。
ここで役立つのが 光を足す工夫です。自然光だけに頼らず、外付けフラッシュやLEDライトを用いると、十分な光量を確保できてシャッタースピードを上げられます。わたし自身はGodox V1を使っていますが、ディフューザーを付けたり、アルミホイルや白い紙で光を柔らかく回したりするだけで、被写体の立体感が一気に増します。光を足すことで「しっかり写す」と「美しく魅せる」を両立できるのです。
光の使い方とライティング

マクロ撮影を始めると、すぐに「光の重要性」に気づかされます。被写体との距離が近くなるぶん、わずかな光の向きや強さの違いが写真の仕上がりに大きく影響します。ここでは自然光と人工光をうまく使い分けるための基本と、僕が実際に試してみた工夫を紹介します。
自然光を味方につける

まず基本は自然光です。柔らかい朝や夕方の光は、花や小物を美しく包み込み、立体感を引き出してくれます。特に逆光で撮影すると、花びらの透明感や葉脈の細部が浮かび上がり、ドラマチックな雰囲気になります。ただし、日中の強い直射日光はコントラストがきつくなりすぎることがあるので、白いレフ板やコピー用紙で反射光を足して影を和らげると自然でバランスのよい仕上がりになります。
フラッシュを活用する

マクロ撮影の世界では、光量不足が大きな課題です。絞りを絞って被写界深度を確保するとシャッタースピードが遅くなり、ブレや被写体の揺れが目立ってしまいます。そんなときに役立つのが外付けフラッシュです。僕は Godox V1を使っていますが、直射ではなくディフューザーを付けて柔らかく回すことで、自然光に近い優しい光を作り出せます。被写体が花なら、光を上からではなく斜め横から当てると、立体感が増してより立派に見えます。
ディフューザーと工夫の小物
フラッシュを使うとどうしても光が硬くなりがちですが、家庭にあるもので十分工夫できます。僕がよくやるのは、コンビニのビニール袋やトレーシングペーパーをフラッシュの前に被せてディフューザー代わりにする方法です。光が拡散されて影が柔らかくなり、被写体が自然に浮かび上がります。また、背景にアルミホイルをクシャッとさせたものを置くと、光が反射してキラキラした玉ボケが生まれ、花の写真が一気に華やかになります。
光の方向で雰囲気を変える
ライティングの面白さは、光の角度を変えるだけで写真の印象ががらりと変わることです。正面から当てれば明るく均一な描写になり、サイドから当てれば陰影が強調されて立体的になります。逆光なら透明感とドラマチックさ、真上からなら落ち着いた印象。小さな被写体だからこそ、光の変化が顕著で、ちょっとした工夫が作品性を大きく高めてくれます。
まとめると、マクロ撮影におけるライティングは「自然光の優しさ」と「人工光のコントロール」をバランスよく使い分けることが鍵です。特別な機材がなくても、身近な工夫で十分に魅力的な写真を撮ることができます。光を操ることで、目に見えない世界がさらに際立ち、自分だけの表現へと繋がっていくのです。
実際に撮った作例紹介
ここまでレンズの特徴や基本テクニック、光の使い方を紹介してきましたが、やはり文章だけでは伝わりにくい部分もあります。そこで、実際に私が NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR Sを使って撮影した作例を通じて、マクロ撮影の魅力を具体的にお見せしたいと思います。
花の細部をクローズアップ

まずは王道の花のマクロ撮影です。トレニアを題材に、花の中心へと続く質感がよく分る花びらをクローズアップしました。紫の濃淡が際立ち、奥に向かって光が差し込む様子はまるで小さなステージのようです。肉眼では見過ごしてしまう花粉や花弁の質感も、マクロで寄ることで繊細に描き出され、生命力を感じさせてくれます。背景には柔らかい光を受けたボケを加え、花の鮮やかさと立体感を際立たせています。こうした小さな工夫が、ありふれた被写体を「作品」へと変えるポイントです。
昆虫を驚かせずに撮る

次に挑戦したのは、夏の公園で出会ったオニヤンマ(トンボ)の撮影です。105mmという焦点距離のおかげで、ある程度距離を取りながらも被写体を大きく写せました。近づきすぎて逃げられてしまう心配が少なく、自然な姿を切り取れるのはこのレンズの大きな強みです。昆虫の目の模様や体の細かな毛まで写し取れたときは、「マクロの世界ってこんなに奥深いのか」と改めて感動しました。
水滴や玉ボケを使った演出

最後に紹介したいのは、水滴と玉ボケを組み合わせた演出です。朝露に濡れた花びらを撮影すると、水滴ひとつひとつが小さなレンズのように働き、背景を反射して幻想的な雰囲気を生み出します。さらにフラッシュを柔らかく当てて光を加えると、水滴がまるで宝石のように輝き、写真全体が華やかになります。こうした「肉眼では決して見られない世界」を表現できるのが、マクロ撮影の醍醐味です。
総じて、マクロ撮影の作例から学べるのは「普段の生活の中に、無限の被写体が潜んでいる」ということです。花や昆虫といった自然の被写体はもちろん、机の上の小物や雨上がりの水滴など、身近なものすべてが新しい表情を見せてくれます。そして、NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR Sはその魅力を余すことなく描写してくれる一本です。
まとめ
マクロ撮影の世界は私たちが普段見ている景色を一変させます。
NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR Sを手にしたことで、花びらの産毛や昆虫の複眼、水滴の輝きといった肉眼では気づかないディテールに出会うことができました。
等倍撮影による迫力、VRによる安定した描写、そして開放f/2.8の美しいボケ味が、このレンズの大きな魅力です。
撮影では三脚を使った安定感、手持ちでの瞬発力、MFとAFの使い分け、さらには絞りや光を工夫することで、思い通りの表現に近づけることができます。また、自然光の柔らかさやフラッシュ+ディフューザーを活かしたライティングは、写真を大きく変化させてくれます。実際の作例を通してもわかるように、身近な花や小物、昆虫でさえ、新しい世界を見せてくれるのがマクロ撮影の魅力です。
ぜひ皆さんも、自分だけの小さな発見を写真に残してみてください。
GSVは企業の大切なデータを守る安全なNASサーバーシステムです。自動バックアップやRAID構成による多重保存で、データの消失リスクを最小限に抑えます。ネットワーク接続だけで社内外から安全にデータにアクセス可能で、異なるOS間でもスムーズな運用が可能です。
スケジュール管理やToDoリストの一元管理機能を備え、チームの業務効率化を支援します。契約期間中の無償アップデートで常に最新機能を利用可能です。
さらに、無停電電源装置(UPS)の標準装備、ウイルス検知システム、柔軟なアクセス制限により、物理的な障害やセキュリティリスクからも企業データを保護。GSVは安全で効率的なデータ管理環境を提供します。
【関連記事】